問13
気象の予報業務の許可を受けた者が予報業務を⾏う際の気象予報⼠の設置等について述べた次の⽂ (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、 下記の1〜5の中から1つ選べ。
(a) 予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報⼠は、その旨を予め気象庁⻑官に届け出なければならない。
(b) 現象の予想を毎⽇ 12 時間⾏う予報業務許可事業者は、当該業務を⾏う事業所に4名以上の専任の気象予報⼠を置かなければならない。
(c) 複数の専任の気象予報⼠の設置が規定されている事業所において規定された⼈数から1名が⽋員となった場合に、1⽇当たりの現象の予想を⾏う時間を変更せずに予報業務を継続するためには、1カ⽉以内に⽋員を補充しなければならない。
本問は、予報業務許可事業者における気象予報士の配置に関する問題です。
本問の解説
(問題)気象の予報業務の許可を受けた者が予報業務を⾏う際の気象予報⼠の設置等について述べた次の⽂ (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、 下記の1〜5の中から1つ選べ。
(a) 予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報⼠は、その旨を予め気象庁⻑官に届け出なければならない。
(b) 現象の予想を毎⽇ 12 時間⾏う予報業務許可事業者は、当該業務を⾏う事業所に4名以上の専任の気象予報⼠を置かなければならない。
(c) 複数の専任の気象予報⼠の設置が規定されている事業所において規定された⼈数から1名が⽋員となった場合に、1⽇当たりの現象の予想を⾏う時間を変更せずに予報業務を継続するためには、1カ⽉以内に⽋員を補充しなければならない。
→ 答えは (a) 誤 (b) 誤 (c) 誤 とする 5 です。
まずは、関係する気象業務法施行規則の規定を見てみましょう。
(予報業務の許可の申請)
第十条 法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 〜 四 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)二 次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類
イ 気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。第十一条の二第一項において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者
ロ 気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者(イに掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行おうとするもの
三 〜 十 (略)
(気象予報士の設置の基準)
第十一条の二 法第十九条の二各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。
一日当たりの現象の予想を行う時間 人員 八時間以下の時間 二人 八時間を超え十六時間以下の時間 三人 十六時間を超える時間 四人 2 法第十七条第一項の許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。)があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
(報告)
第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 〜 五 (略)
六 第十条第二項第一号(ニを除く。)から第六号まで又は第四十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合
七 〜 八 (略)
2 〜 5 (略)
気象業務法施行規則「https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101/」
では、本問の選択肢と見比べてみましょう。
本問の解説:(a)について
(問題)予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報⼠は、その旨を予め気象庁⻑官に届け出なければならない。
→ 答えは 誤 です。
気象予報士が、予報業務許可事業者(予報業務の許可を受けた事業者)で天気予報などの業務に従事する場合、その事業者は、気象予報士の氏名や登録番号などを、予報業務の許可申請時や、従事する気象予報士が変更になった場合に、気象庁長官に届け出ることになっています。
つまり、この手続きは「事業者」が行うものであり、気象予報士本人が気象庁長官に届け出ることではありませんので、答えは 誤 となります。
本問の解説:(b)について
(問題)現象の予想を毎⽇ 12 時間⾏う予報業務許可事業者は、当該業務を⾏う事業所に4名以上の専任の気象予報⼠を置かなければならない。
→ 答えは 誤 です。
予報業務許可事業者には、下表のように、事業所ごとに「1日あたりの現象の予想を行う時間」に応じた人数以上の「専任の気象予報士」を配置することが義務づけられています。
| 1日あたりの現象の予想を行う時間 | 人員 |
| 8時間以下の時間 | 2人 |
| 8時間を超え 16 時間以下の時間 | 3人 |
| 16 時間を超える時間 | 4人 |
4人以上の気象予報士を置かなければならないとされているのは、1日当たり「 12 時間 」ではなく「 16 時間 」を超えて現象の予想を行う場合ですので、答えは 誤 となります。
本問の解説:(c)について
(問題)複数の専任の気象予報⼠の設置が規定されている事業所において規定された⼈数から1名が⽋員となった場合に、1⽇当たりの現象の予想を⾏う時間を変更せずに予報業務を継続するためには、1カ⽉以内に⽋員を補充しなければならない。
→ 答えは 誤 です。
予報業務許可事業者には、問題 (b) で見たように、事業所ごとに「1日あたりの現象の予想を行う時間」に応じた人数以上の「専任の気象予報士」を配置することが義務づけられています。
もし、専任の気象予報士が欠員となり、その基準を満たさなくなった場合、事業者は「1か月以内」ではなく「2週間以内」に、以下のどちらかの対応をしなければなりません。
- 不足している気象予報士を補充する
- 予想を行う時間を短縮して、必要な人数の基準に合わせる
したがって、複数の専任の気象予報⼠の設置が規定されている事業所において規定された⼈数から1名が⽋員となった場合に、1⽇当たりの現象の予想を⾏う時間を変更せずに予報業務を継続するためには、「1カ⽉以内に⽋員を補充」ではなく「2週間以内に基準を満たす措置をとる」必要がありますので、答えは 誤 となります。
以上より、本問の解答は、(a) 誤 (b) 誤 (c) 誤 とする 5 となります。
試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。
当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。
また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

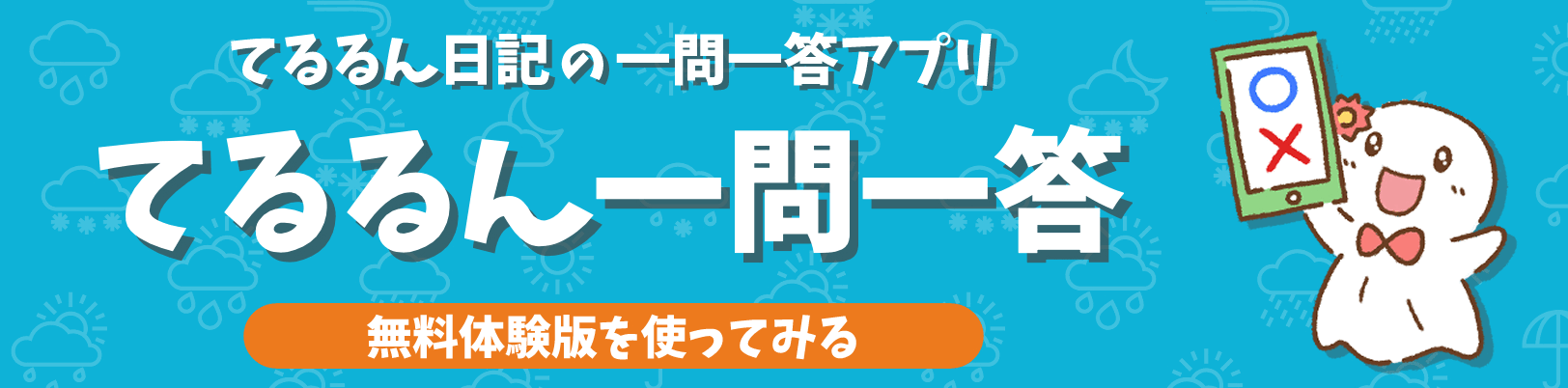


コメント