問15
災害対策基本法に定められた対策に関する次の⽂ (a) 〜 (d) の下線部の正誤について、下記の1〜5の中から正しいものを1つ選べ。
(a) 市町村は、基礎的な地⽅公共団体として、当該市町村の地域に係る防災に関する計画(市町村地域防災計画)を作成し、法令に基づきこれを実施する責務を有する。
(b) 市町村内の⼀定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に、当該地区における防災活動に関する計画である地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
(c) 都道府県の地域について災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
(d) 中央防災会議は、災害及び災害の防⽌に関する科学的研究の成果並びに発⽣した災害の状況やこれに対して⾏われた災害応急対策の効果を勘案して、5年ごとに防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには修正しなければならない。
本問は、災害対策基本法における計画および災害対策基本本部の設置に関する問題です。
本問の解説
(問題)災害対策基本法に定められた対策に関する次の⽂ (a) 〜 (d) の下線部の正誤について、下記の1〜5の中から正しいものを1つ選べ。
(a) 市町村は、基礎的な地⽅公共団体として、当該市町村の地域に係る防災に関する計画(市町村地域防災計画)を作成し、法令に基づきこれを実施する責務を有する。
(b) 市町村内の⼀定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に、当該地区における防災活動に関する計画である地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
(c) 都道府県の地域について災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
(d) 中央防災会議は、災害及び災害の防⽌に関する科学的研究の成果並びに発⽣した災害の状況やこれに対して⾏われた災害応急対策の効果を勘案して、5年ごとに防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには修正しなければならない。
→ 答えは (d) のみ誤り とする 4 です。
まずは、関係する気象業務法施行規則の規定を見てみましょう。
(市町村の責務)
第五条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
2 ~ 3 (略)
(都道府県災害対策本部)
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
2 ~ 8 (略)
(防災基本計画の作成及び公表等)
第三十四条 中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
2 (略)
(市町村地域防災計画)
第四十二条の二 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
2 ~ 5 (略)
災害対策基本法「https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223/」
では、本問の選択肢と見比べてみましょう。
本問の解説:(a)について
(問題)市町村は、基礎的な地⽅公共団体として、当該市町村の地域に係る防災に関する計画(市町村地域防災計画)を作成し、法令に基づきこれを実施する責務を有する。
→ 答えは 正 です。
市町村は「基礎的な地方公共団体」として、地域の安全を守る重要な役割を担っています。
特に、防災に関しては「市町村地域防災計画」の策定と、その計画に基づく具体的な施策の実施が法的に義務付けられています。
この責務は「災害対策基本法 第五条 第1項」で以下のように定められています。
市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
つまり、市町村は災害発生時のみならず、平時から防災・減災に向けた取り組みを行う必要があるということです。
これには、住民への情報提供、避難体制の整備、地域特性に合わせたハザードマップの作成などが含まれます。
したがって、市町村は、基礎的な地⽅公共団体として、当該市町村の地域に係る防災に関する計画(市町村地域防災計画)を作成し、法令に基づきこれを実施する責務を有しますので、答えは 正 となります。
本問の解説:(b)について
(問題)市町村内の⼀定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に、当該地区における防災活動に関する計画である地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
→ 答えは 正 です。
市町村内における一定の地区の居住者及び事業者は、その地域の防災力向上に資する主体的な取り組みとして、共同して地区防災計画の提案を行うことができます。
この提案は、市町村地域防災計画の一部として位置付けられ、市町村防災会議に対して行われます。
そして、その際には、提案に係る「地区防災計画の素案」を添付する必要があります。
この制度は「災害対策基本法 第四十二条の二 第1項」で以下のように定められています。
地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
つまり、住民や事業者が自らの地域における防災活動に関して、具体的な提案を行うことが可能であり、地域主体の防災体制の形成が促されているのです。
これには、実情に即した避難計画や防災資機材の整備、防災訓練の実施体制などを住民・事業者が主体的に企画する意義があります。
したがって、市町村内の⼀定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に、当該地区における防災活動に関する計画である地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければなりませんので、答えは 正 となります。
本問の解説:(c)について
(問題)都道府県の地域について災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
→ 答えは 正 です。
都道府県知事は、地域の安全確保と災害対応の陣頭指揮を担う立場として、重大な責務を負っています。
特に、災害が発生した、またはそのおそれがある状況下では、防災の推進を図る必要があると判断した場合に、都道府県地域防災計画に基づいて「都道府県災害対策本部」を設置することができます。
この措置は「災害対策基本法 第二十三条 第1項」で以下のように定められています。
都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
つまり、災害対応の初動を迅速かつ組織的に行うための制度的枠組みとして、本部設置が法令によって認められているのです。
これには、被害状況の把握、住民の安全確保、避難誘導の指揮、支援物資の調整など、災害時に必要な諸対策を円滑に実施するための司令塔的な役割が含まれます。
したがって、都道府県の地域について災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができますので、答えは 正 となります。
本問の解説:(d)について
(問題)中央防災会議は、災害及び災害の防⽌に関する科学的研究の成果並びに発⽣した災害の状況やこれに対して⾏われた災害応急対策の効果を勘案して、5年ごとに防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには修正しなければならない。
→ 答えは 誤 です。
中央防災会議は、国の防災に関する基本方針を策定・見直しする責任を担う機関として、災害への対応力強化と予防策の向上に貢献しています。
特に、防災基本計画については、過去に発生した災害の状況や、それに対して講じられた応急対策の効果、そして災害の予防に関する科学的研究の成果などを踏まえて、必要に応じて計画の見直しを行うことが求められています。
この見直しの頻度については、「災害対策基本法 第三十四条 第1項」で以下のように規定されています。
中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
つまり、「5年ごと」ではなく、「毎年」の検討が義務付けられています。
これは災害の性質や影響が年々変化し得ることを踏まえ、柔軟かつ迅速に計画を更新する体制を確保するための制度です。
これには、地震や台風などの自然災害だけでなく、複合災害や新たなリスクへの対応策も含まれており、計画の実効性を高めるために毎年点検と改善を行うことが極めて重要です。
したがって、中央防災会議は、災害及び災害の防⽌に関する科学的研究の成果並びに発⽣した災害の状況やこれに対して⾏われた災害応急対策の効果を勘案して、「5年ごとに」ではなく「毎年」防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには修正しなければなりませんので、答えは 誤 となります。
以上より、本問の解答は、(d) のみ誤り とする 4 となります。
試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。
当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。
また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

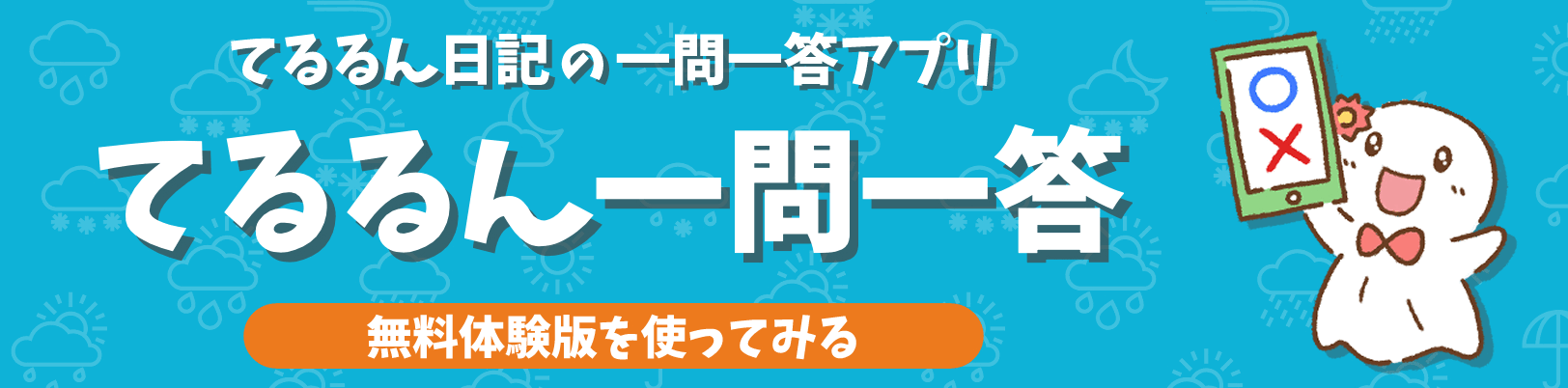


コメント