問4
数値予報とその予測対象である⼤気現象について述べた次の⽂章の下線部 (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から 1 つ選べ。
⼤気現象には様々な時間空間スケールを持つものがあるが、⼀般に、(a) 数値予報モデルで予測可能な現象の⽔平スケールの下限は、⽔平格⼦間隔が⼩さいほど⼩さくなる。また、数値予報が予測できる⼤気現象は、数値予報モデルによっても異なる。数値予報において組織化された積乱雲からもたらされる強い降⽔の予測精度を向上させるには、(b) プリミティブ⽅程式系を基礎⽅程式とする数値予報モデルを⽤いる必要があり、物理過程として最も重要な部分は、(c) 地⾯からの蒸発や⽇射による地⾯の加熱を考慮した下部境界からの熱・⽔蒸気供給のパラメタリゼーションである。
本問は、数値予報とその予測対象である⼤気現象に関する問題です。
本問の解説:(a) について
(問題)⼤気現象には様々な時間空間スケールを持つものがあるが、⼀般に、(a) 数値予報モデルで予測可能な現象の⽔平スケールの下限は、⽔平格⼦間隔が⼩さいほど⼩さくなる。
→ 答えは 正 です。
数値予報モデル では、大気の状態を数値的に表すために、対象領域(地球全体や特定地域)を格子状に分割し、各格子点で気温・気圧・風速などの物理量を計算します。
このとき、モデルの水平格子間隔(=水平方向の格子点同士の間隔)が小さいほど、より細かい(小さい)スケールの現象を表現できるようになります。
一般に、数値予報モデルが表現できる現象の最小スケールは、
水平格子間隔の5〜8倍程度とされています。
- 全球モデル(GSM):水平格子間隔 約13km → 表現可能な最小スケールは約65〜104km
- メソモデル(MSM):水平格子間隔 約5km → 表現可能な最小スケールは約25〜40km
このように、水平格子間隔が小さくなるほど、数値予報モデルが表現できる現象の水平スケールの下限も小さくなるのです。
したがって、一般に、数値予報モデルで予測可能な現象の⽔平スケールの下限は、⽔平格⼦間隔が⼩さいほど⼩さくなりますので、答えは 正 となります。
本問の解説:(b) について
(問題)また、数値予報が予測できる⼤気現象は、数値予報モデルによっても異なる。数値予報において組織化された積乱雲からもたらされる強い降⽔の予測精度を向上させるには、(b) プリミティブ⽅程式系を基礎⽅程式とする数値予報モデルを⽤いる必要がある。
数値予報モデルが基礎として用いる方程式系には、プリミティブ方程式系 と 非静力学方程式系 の2種類があります。
プリミティブ方程式系 とは、大気の運動方程式に静力学近似を導入し、鉛直方向では気圧傾度力と重力が釣り合っていると仮定する方程式系のことです。
この近似により鉛直加速度の計算を省略できるため、計算量を大幅に減らすことができます。
こうした特徴から、プリミティブ方程式系は水平方向のスケールが数百km以上に及ぶ総観規模現象(低気圧や前線など)の予測に適しています。
しかし、鉛直運動が強い現象、特に積乱雲のような対流活動を詳細に表現することは苦手です。
プリミティブ⽅程式系を基礎⽅程式とする数値予報モデルの代表例としては、全球モデル(GSM)が挙げられます。
非静力学方程式系 とは、静力学近似を行わず、大気の運動を鉛直方向の加速度まで含めて計算する方程式系です。
そのため、積乱雲や局地的な豪雨など、鉛直運動の強い現象を直接表現することが可能です。
非静力学方程式系を基礎⽅程式とする数値予報モデルの代表例としては、メソモデル(MSM)や 局地モデル(LFM)が挙げられます。
つまり、組織化された積乱雲による強い降水の予測精度を高めるには、鉛直運動を正確に扱える非静力学モデルを用いる必要があります。
したがって、数値予報において組織化された積乱雲からもたらされる強い降⽔の予測精度を向上させるには、「プリミティブ⽅程式系」ではなく「非静力学方程式系」を基礎⽅程式とする数値予報モデルを⽤いる必要がありますので、答えは 誤 となります。
本問の解説:(c) について
(問題)組織化された積乱雲からもたらされる強い降⽔の予測精度を向上させるための物理過程として最も重要な部分は、(c) 地⾯からの蒸発や⽇射による地⾯の加熱を考慮した下部境界からの熱・⽔蒸気供給のパラメタリゼーションである。
→ 答えは 誤 です。
数値予報モデルでは、格子間隔より小さいスケール(サブグリッドスケール)の現象を直接表現することができないため、それらの影響を格子点の物理量として近似的に反映する パラメタリゼーション が用いられます。
代表的な物理過程には、【放射過程】、【積雲対流過程】、【地表面過程】、【境界層乱流】、【重力波抵抗】などがあります。
問題文の「地面からの蒸発や日射による加熱を考慮した熱・水蒸気供給のパラメタリゼーション」は、これらのうち【地表面過程】に該当します。
地表面は大気の下部境界として熱や水蒸気を供給し、予報精度向上に重要な役割を果たします。
しかし、組織化された積乱雲がもたらす強い降水の予測精度を高める上でより重要なのは、【積雲対流過程】の表現です。
積乱雲は数百mから数kmのスケールで発達し、雲内部での水の相変化や熱・水蒸気・運動量の鉛直輸送が降水強度を大きく左右します。
このため、これらを適切に扱う【積雲対流過程】のパラメタリゼーションが強い降水の再現性を大きく左右するのです。
したがって、組織化された積乱雲からもたらされる強い降⽔の予測精度を向上させるための物理過程として最も重要な部分は、「地⾯からの蒸発や⽇射による地⾯の加熱を考慮した下部境界からの熱・⽔蒸気供給を表現する【地表面過程】のパラメタリゼーション」ではなく「格子間隔よりも小さいスケールの積雲対流に伴う水の相変化や熱・水・運動量の鉛直輸送の効果を表現する【積雲対流過程】のパラメタリゼーション」ですので、答えは 誤 となります。
以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 誤 (c) 誤 とする 3 となります。
試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。
当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。
また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

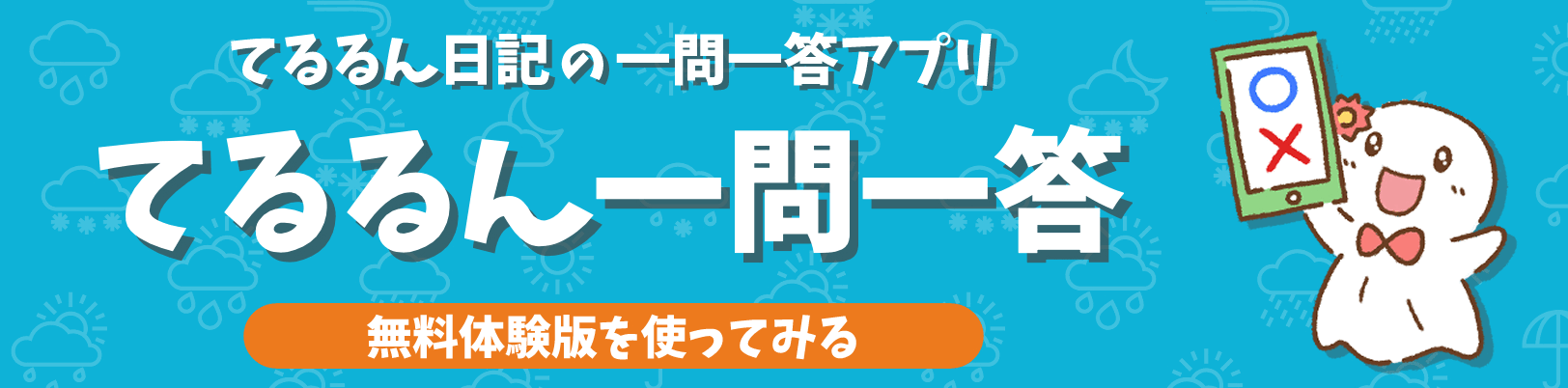


コメント