問5
気象庁の数値予報において初期値を作成する客観解析における観測データの取扱いについて述べた次の⽂ (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、 下記の1〜5の中から 1 つ選べ。
(a) 観測データの品質を⼀定期間モニタリングした結果、品質が低いと判断された観測地点のデータは、数値予報システムの客観解析には使⽤されない。
(b) 気温や⾵などの観測データは、第⼀推定値と⽐較され、その差が定められた基準を超える場合は客観解析には利⽤されない。
(c) ラジオゾンデによる⾼層気象観測は⼤気を直接観測しており精度が⾼いため、品質管理を⾏った上で、観測値そのものを観測地点の直近の格⼦点の解析値としている。
本問は、気象庁の数値予報において初期値を作成する客観解析における観測データの取扱いに関する問題です。
本問の解説:(a) について
(問題)観測データの品質を⼀定期間モニタリングした結果、品質が低いと判断された観測地点のデータは、数値予報システムの客観解析には使⽤されない。
→ 答えは 正 です。
客観解析 とは、不規則に分布した観測データと、過去の予測値(=第一推定値)を、観測誤差やその統計的性質も考慮しながら統合し、数値予報モデルが利用できるように規則的な格子点上の大気の状態(=初期値)を作成する解析手法のことです。
数値予報を行うためには、まず三次元空間のすべての格子点に初期値(=ある時刻の気温、風、水蒸気量などの大気の状態)を与える必要があります。
しかし、実際の観測データは観測地点が不規則に分布しており、そのままでは数値予報で使えません。
そこで、観測値と過去の予測値(第一推定値)を比較・統合して、
規則的な格子点上の値に変換する作業を行います。
これを 客観解析 といいます。
初期値が正確であるほど、精度の高い数値予報につながるため、容観解析の手法にも多くの改良が重ねられてきました。
現在は、最新の観測データをいち早く取り込むために計算負荷を抑えた 三次元変分法 という手法や、数値予報モデルを実行して少しずつ解析値を修正させることにより、第一推定値と観測値との間で最もバランスのとれた最適な解析値を作成する 四次元変分法 という手法などが用いられています。
観測データには、測器の故障などが原因で異常値が混入することがあります。
客観解析でこの異常値をそのまま使うと、初期値の精度が低下するだけでなく、場合によっては初期値解析の処理が異常終了する原因となってしまいます。
そこで行われるのが 品質管理(QC:Quality Control)です。
品質管理には主に2種類あります。
- リアルタイムQC :観測データが入電した直後に、自動的に異常値を検出・除去する手法です。例えば、観測値と第一推定値を比較し、その差が大きいデータを異常値と判断して、その後の客観解析から除外されます。
- 非リアルタイムQC :数日〜数か月といった一定期間の観測データの傾向をモニタリングし、測器の故障や設置環境の変化などで長期的に品質が低下している観測地点を検出する手法です。品質が悪いと判断された地点はリスト化され、その後の客観解析から除外されます。
非リアルタイムQCでは、例えば、海上に設置された気象観測用ブイが損傷して、異常な観測データが通報され続ける場合などがあげられます。
こうしたデータはあらかじめリスト化され、「品質が低い」と判断された観測データは除去され客観解析には使われません。
したがって、観測データの品質を⼀定期間モニタリングした結果、品質が低いと判断された観測地点のデータは、数値予報システムの客観解析には使⽤されませんので、答えは 正 となります。
本問の解説:(b) について
(問題)気温や⾵などの観測データは、第⼀推定値と⽐較され、その差が定められた基準を超える場合は客観解析には利⽤されない。
→ 答えは 正 です。
数値予報の初期値を作成する客観解析では、観測データの品質を確認するために 品質管理(QC:Quality Control)が行われます。
その代表的な手法のひとつが、観測値と第一推定値を比較する手法で、これは観測データが入電した直後に自動で行われる リアルタイムQC に分類されます。
第一推定値 とは、前回の数値予報の結果(解析値)を、数値予報モデルで時間的に進めて、現在時刻の大気の状態を予想したものです。
(難しい言葉で言うと、直前の解析値から数値予報モデルで時間積分して得られた予測値です。)
第一推定値は精度が比較的高いため、観測値との差が大きい場合、その観測データは異常値である可能性が高いと判断されます。
このため、観測値と第一推定値との差があらかじめ定められた基準を超える観測データは、客観解析には利用されません。
また、周囲の観測データとも比較し、もし周囲の値と大きく異なっていれば、そのデータの信頼性は低いとみなされ、客観解析から除外されます。
このように、第一推定値や周囲の観測との比較を通して信頼性の低い観測値を除去することで、初期値の精度を保っています。
したがって、気温や⾵などの観測データは、第⼀推定値と⽐較され、その差が定められた基準を超える場合は客観解析には利⽤されませんので、答えは 正 となります。
本問の解説:(c) について
(問題)ラジオゾンデによる⾼層気象観測は⼤気を直接観測しており精度が⾼いため、品質管理を⾏った上で、観測値そのものを観測地点の直近の格⼦点の解析値としている。
→ 答えは 誤 です。
ラジオゾンデ とは、上空の気温、湿度などの気象要素を直接測定するセンサーと、測定した情報を無線送信する無線送機を備えた気象観測機器です。
気球にラジオゾンデを吊り下げて飛揚することで、上空約30kmまでの気温・湿度・風向・風速をそれぞれ気圧(高度)とともに直接観測しています。

画像出典:気象庁ホームページ「高層気象観測(GPSゾンデ観測)」
ラジオゾンデは大気を直接観測するため、気象衛星などのリモートセンシングによる観測より精度が高いです。
しかし、それでも観測値には、わずかな誤差を含むため、この観測値をそのまま数値予報の解析値として使うことはありません。
数値予報の初期値を作る データ同化 では、ラジオゾンデの観測値と、直前の数値予報の結果から得られる第一推定値を比較し、それぞれの誤差特性に基づいて重みをつけ、両者を組み合わせて解析値を作成します。
ラジオゾンデの観測誤差は衛星観測よりも小さい値が設定されるため、解析値は観測値寄りになりますが、それでも観測値そのものを直接格子点に割り当てることはありません。
したがって、ラジオゾンデの観測データは、品質管理を⾏った上で、「観測値そのものを観測地点の直近の格⼦点の解析値としている」わけではなく、「観測値と第一推定値を比較し、それぞれの誤差特性に基づいて重みをつけ、両者を組み合わせて解析値を作成しています」ので、答えは 誤 となります。
以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 正 (c) 誤 とする 2 となります。
試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。
当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。
また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

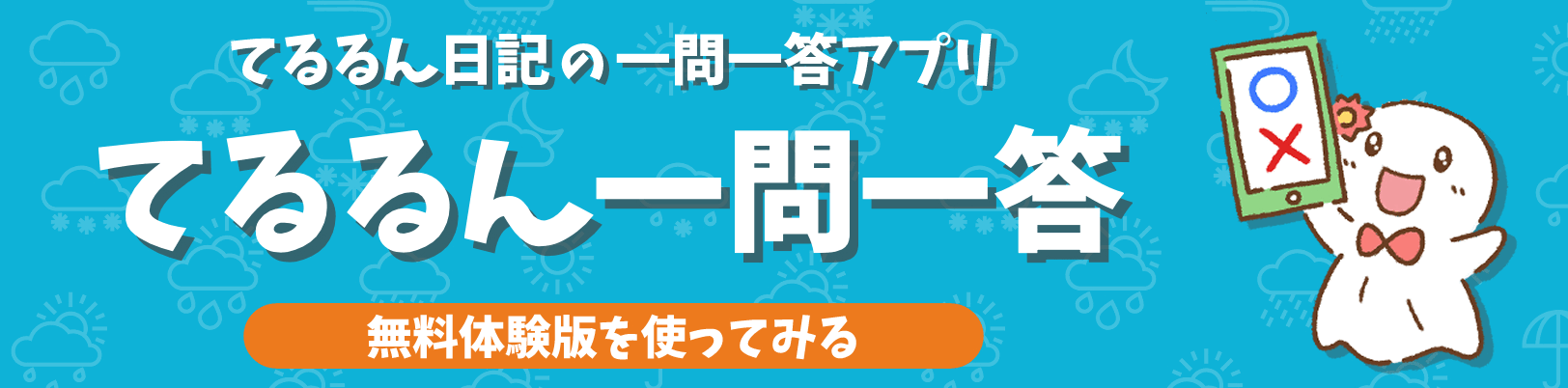


コメント