問13
気象予報士について述べた次の文 (a) ~ (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。
(a) 気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるためには、気象庁長官の承認を受けなければならない。
(b) 気象予報士は、住所を変更したときには遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。
(c) 気象予報士は、気象の予報業務の許可を受けた事業者のもとで気象の予報を行おうとするときには、予めその旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(d) 気象予報士が死亡したとき、その相続人は、遅滞なくその旨を気象庁長官に届け出なければならない。
本問は、気象予報士となるための登録、登録の変更、登録の抹消および気象予報士が行う業務に関する問題です。
本問の解説
(問題)気象予報士について述べた次の文 (a) ~ (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。
(a) 気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるためには、気象庁長官の承認を受けなければならない。
(b) 気象予報士は、住所を変更したときには遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。
(c) 気象予報士は、気象の予報業務の許可を受けた事業者のもとで気象の予報を行おうとするときには、予めその旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(d) 気象予報士が死亡したとき、その相続人は、遅滞なくその旨を気象庁長官に届け出なければならない。
→ 答えは (a) 誤 (b) 正 (c) 誤 (d) 正 とする 4 です。
まずは、関係する気象業務法と気象業務法施行規則の規定を見てみましょう。
(予報業務の許可)
第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2 〜 3 (略)
(登録)
第二十四条の二十 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第二十四条の二十四 気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第二十四条の二十五 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。
一 死亡したとき。
二 〜 四 (略)
2 気象予報士が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
気象業務法「https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000165」
(予報業務の許可の申請)
第十条 法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 予報業務の目的
三 予報業務の範囲
イ 予報の種類
ロ 対象としようとする区域
ハ 火山現象の予報にあつては、対象としようとする火山
ニ 気象関連現象予報業務にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別
四 予報業務の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
二 次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類
イ 気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。第十一条の二第一項において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者
ロ 気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者(イに掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行おうとするもの
三 〜 十 (略)
3 〜 4 (略)
(気象予報士名簿の登録事項)
第三十四条 法第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所並びに試験の合格年月日及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。
2 (略)
(報告)
第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 〜 五
六 第十条第二項第一号(ニを除く。)から第六号まで又は第四十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合
七 〜 八
2 〜 5 (略)
気象業務法施行規則「https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101/」
では、本問の選択肢と見比べてみましょう。
本問の解説:(a)について
(問題)気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるためには、気象庁長官の承認を受けなければならない。
→ 答えは 誤 です。
気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるためには、気象庁長官の「承認」ではなく「登録」を受けなければなりませんので、答えは 誤 となります。
本問の解説:(b)について
(問題)気象予報士は、住所を変更したときには遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。
→ 答えは 正 です。
気象予報士名簿への登録事項は、住所、試験の合格年月日、気象予報士試験合格証明書の番号の3点です。
これらの内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければなりませんので、答えは 正 となります。
本問の解説:(c)について
(問題)気象予報士は、気象の予報業務の許可を受けた事業者のもとで気象の予報を行おうとするときには、予めその旨を気象庁長官に届け出なければならない。
→ 答えは 誤 です。
気象予報士が、予報業務の許可を受けた者の下で、予報業務に従事しようとするときは、事業所ごとに置かれる気象予報士の変更に該当することになります。
このため、予報業務の許可を受けた者が、変更の報告書を、変更事項の発生後、遅滞なく気象庁長官に提出しなければなりません。
なお、新たに予報業務の許可を受けようとする場合は、許可を受けようとする者が、予報業務許可申請書に、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類を添付しなければなりません。
したがって、気象予報士が、予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする場合は、予報業務の許可を受けた者が、気象予報士の変更の報告書を、変更後遅滞なく気象庁長官に提出しなければならず、気象予報士自らが行う義務はありませんので、答えは 誤 となります。
本問の解説:(d)について
(問題)気象予報士が死亡したとき、その相続人は、遅滞なくその旨を気象庁長官に届け出なければならない。
→ 答えは 正 です。
気象予報士が死亡したとき、その相続人は、遅滞なくその旨を気象庁長官に届け出なければなりませんので、答えは 正 となります。
以上より、本問の解答は、(a) 誤 (b) 正 (c) 誤 (d) 正 とする 4 となります。
試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。
当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。
また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

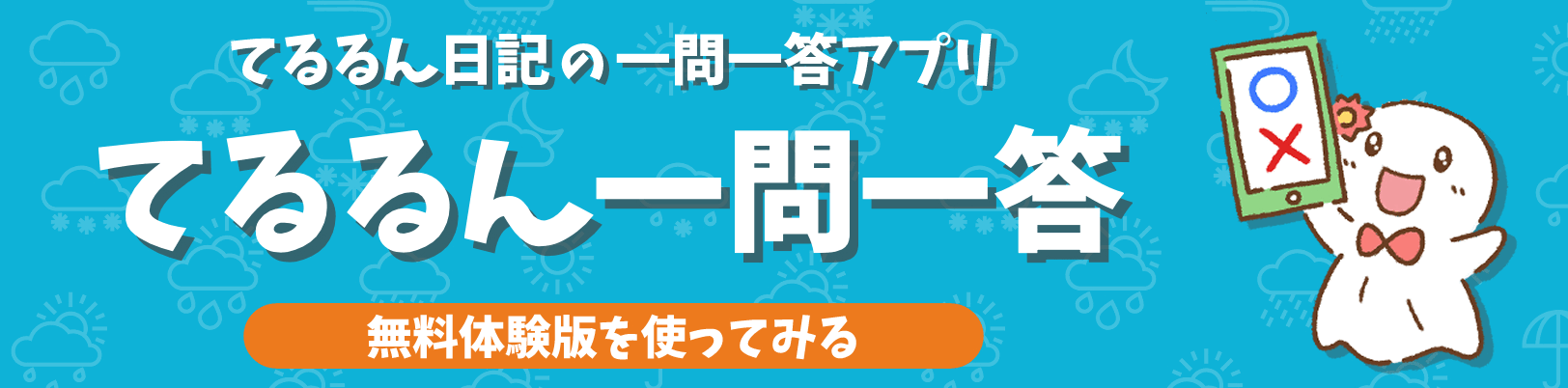


コメント